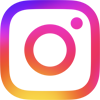第9回 ケーススタディ「長時間対応」(公開日:2025年8月)
- ホーム
- ACAPの取り組み
- カスタマーハラスメント対策特集
- 第9回 ケーススタディ「長時間対応」(公開日:2025年8月)
今回からは、これまでにいただいた質問や事例を一緒に考えていきたいと思います。
【ご相談内容】
50代男性、頻繁に入電がある方への対応について。
毎回、商品に関してではなく、会社への批判や身の上話の繰り返しで、早々に切り上げようとしたところ激怒し、その後1時間以上拘束される事案がありました。
これまで、1次応対者がお申し出内容を傾聴し、管理者である私が比較的厳しく応対してきたのですが、所要時間が2時間以上におよぶ日もあり、上司から対応時間を短縮できないか検討するよう求められました。このようなケースではもっと毅然と対応すべきでしょうか。

■対応方針とお客さまへの伝え方
お客さまに寄り添う姿勢は大事ですが、このような場面の中で30分以上にわたり話を聞く必要はありません。対応時間の限度は各社で決めておくことをお勧めします。
この相談事例での対応方針とお客さまへの伝え方を考えてみましょう。
「このお電話は商品やサービスに関する窓口となっております。他にご用件はございますか」「他にもお待ちのお客さまがいらっしゃいます。本日は失礼いたします」とお伝えして切電してよいケースです。この場合、対応の「中止」ではなく「中断」を判断します。再入電があれば対応を再開します。再入電時に同じ話であれば「先ほどお伝えした通りです。失礼いたします」とお伝えし切電します。このような場合は30分も聞かずに同じ話であると判断した時点で切電して構いません。
- 対応では「中止」だけではなく「中断」の考え方を持つ
-
伝え切れていないことなどがある場合「中止」ではなく「中断」の考えを持つことにより対応の幅が広がります。「中止」は今後一切の対応を行わない、「対応終了」とすることになります。一方「中断」は本日の対応はここまでとする、といった考え方です。お客様から再入電があった場合には対応する、または事業者側から連絡をするなどの余地を残した対応方法となります。

■組織として判断する
対応の「中断」や「中止」は管理者が組織として判断します。お客さまにお伝えするのは1次応対者でも管理者でも構いません。カスタマーハラスメント対応方針やマニュアルで、切電の手順が明記されていると管理者としても判断がしやすくなります。
■切電できない理由
切電できない理由として、一方的に切電した場合、お客さまが怒って再度電話をしてくると嫌だ、怖い、面倒なことになる、といった声を耳にします。まず、誠意をもって対応することが大前提ですが、組織としては、怒らせてしまっても仕方がないと割り切ることです。1次応対者に対してもこの考えが共有できていれば、負荷がかかりません。
■カスタマーハラスメント対応方針の公表
カスタマーハラスメント対応方針が公表できていれば「私どもはカスタマーハラスメント対応方針を公表しております。本日は失礼いたします」と伝えることができます。ただし、安易に「カスタマーハラスメント」という言葉を使うことは控え、数回忠告しても聞き入れてもらえず、行き過ぎた行為が続いた場合に用いると良いです。
このようなお客さまは今後も入電の可能性があります。これまでの入電件数、入電時間、発言内容を「時系列」に記録しておきます。管理者からの対応方針も記録しておくと良いでしょう。
■お客さまに寄り添いつつ時間を区切った対応を行う
ここで、別の角度からこのお客さまをとらえてみましょう。このお客さまが商品をよく購入してくれている方であったり、会社のファンの方であったりする可能も考えられます。特に乱暴な言葉や威圧的でもないが、対応が長時間にわたってしまう場合はどう対応したら良いでしょうか。
このような場合も事前に対応方針を定めておきます。いつもお電話いただくことに対するお礼を伝え、寄り添う姿勢を示しつつも、例えば、10分間だけ話を聞くなど時間を区切った対応方針を定めておくと良いでしょう。入電時は多くを話さず「あいづち」や「復唱」などの繰り返しで良いです。組織としての対応方針が決まっていれば1次応対者に過度の負荷がかかることはありません。カスタマーハラスメントを未然に防ぐためにも組織で対応することが肝要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。