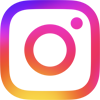第10回 ケーススタディ「返答に納得されない方への対応」(公開日:2025年9月)
- ホーム
- ACAPの取り組み
- カスタマーハラスメント対策特集
- 第10回 ケーススタディ「返答に納得されない方への対応」(公開日:2025年9月)
今回も、これまでにいただいた質問や事例を一緒に考えていきたいと思います。
【ご相談内容】
40代男性、返答内容に納得されない方への対応について
お客さまの使用方法に起因する商品の破損であったため、返品対応はできない旨お伝えしましたが、納得していただけませんでした。お客さまは、「あんたの上司に相談した上で連絡してきたら納得する」と大声で言う。上司と話した上で連絡していると伝えても納得していただけず、同じことを繰り返し主張。再度連絡する日時を確認するも「それを言うと悪用される」と答えず。
後日、お客さまより「行政等に相談したが、前回の説明は間違っている。今後の人のために間違っていることを教えるために連絡した」と入電有り。このようなお客さまにはどこまで対応したらよいでしょうか。

■対応方針とお客さまへの伝え方
お客さまに納得していただくために、できる限りの説明を行うことは大事ですが、上司と話し、方針を伝えた上で納得されない場合、納得していただけなくても仕方がないという判断を組織で行います。
お客さまへの伝え方の一例は次のとおりです。「お客さま、私どもとしてのご説明は以上となります。他にご質問がなければ、本日の対応はここまでとさせていただきます。失礼いたします」と伝えて対応を終了させます。
■対応のポイント
お客さまの希望や要求に対して、どこまで対応できるかを組織として判断します。1次応対者が即答する必要はありません。常識的な返答までの日数や時間をお伝えした上で、折り返し連絡の了解をいただきます。
その際に「遅すぎる」「今すぐ答えろ」などと言われた場合は、「関連部門も含めてきちんと確認する必要があります。恐れ入りますが、ご容赦いただけますでしょうか」と切り返します。
お客さまが回答を急ぐ合理的な理由が無い場合、ご納得いただけないとしても、「恐れ入りますが、○日までお待ちいただけない場合、本日はこれで失礼いたします」とだけお伝えし、通話を終了します。
回答日に架電し伝えた内容にご理解いただけなかった場合、「弊社として確認した結果でございます。私どもからお伝えできることは以上となります。失礼いたします」と伝えて切電します。
「行政等に相談したが、前回の説明は間違っている」とのコメントがありましたが、具体的な要望などが含まれていない場合、企業としては特に触れる必要はありません。〇〇の消費生活相談センターで聞いた、などと話が出た場合は、「窓口1本化の原則」に則り対応する必要があります。
具体的な内容を確認した上で、状況によっては「行政を(解決の)窓口としてお客さまがお選びになったのであれば、窓口を行政に1本化する必要がございます。恐れ入りますが、私どもからお答えすることは差し控えます」とお伝えできます。
■対応を「中断」「中止」するためには「正当な理由」と「努力した姿勢」が必要
当コラムにおいて、対応の「中断」や「中止」を判断する際は「正当な理由」と「努力した姿勢」が必要とお伝えしてきました。まずは対応を「中断」する要件となる「正当な理由」を集め記録します。
「あんたの上司に相談した上で連絡してきたら納得する」との発言は一方的です。「上司と話した上で連絡している」と伝えているにも関わらず納得しないで同じ要求を繰り返した時点で、不当な要求内容といえます。
また、要求時の態度が「大声」とありますが、暴言が含まれていた場合には、その内容も正確に記録する必要があります。この時点で何度目の入電であるか、1回当たりの通話時間などを正確に記録します。
「努力した姿勢」に関してはどうでしょうか。上司と相談したことや、確認結果をお伝えするためにお客さまの都合のよい日時を尋ねたことは解決に向けて努力した姿勢を示したことになります。
■「努力した姿勢」を示すためには「忠告」と「警告」を意識して伝える
当ケースの現時点では、「努力した姿勢」を示すための「忠告」や「警告」が十分とはいえません。次回入電時に、納得せず同様の行為があった場合、まずは「忠告」として「私どもからのご説明は以上となります」「大きな声でお話しすることはお控えください」と丁寧に伝えます。
その上で、納得せずに同様の主張を繰り返される場合は、次のように「警告」します。
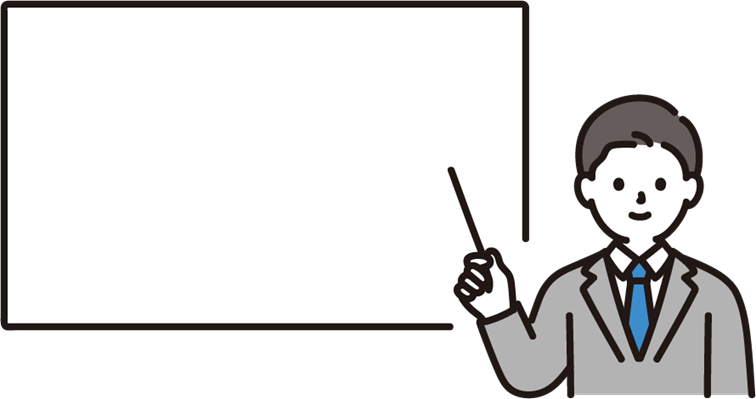
「〇回にわたってご説明しましたがご理解いただけないようなので、このまま対応を続けることは難しくなります」または「大きな声でお話しすることをお止めいただくようお願いしましたが、お止めいただけておりません。恐れ入りますが、私どものルールとして対応を中止せざるを得ません」とお伝えします。
その上で、不当な要求や大声、暴言などの行き過ぎた行為が続く場合には切電します。
「忠告」を行った上での「警告」となりますが、ステップを踏んだ対応が必要です。丁寧にステップを踏んで「努力した姿勢」を示したことを記録し「時系列」に残しておくことが大事です。
■業界による対応の違い
対応の「中断」は、その場の対応を終えることで、日を改めて対応する、または、再入電があった際に対応する方法であり、業界を問わず対応方針の1つとして判断することができます。
対応の「中止」については、再入電があっても一切対応しない方法です。そのため、金額が張る住宅や自動車関連、一生涯の付き合いとなる金融・保険などの場合「中止」を判断することは組織としても難しいと思われます。お客さまの要求や行為が刑法に触れる場合を除くと、対応を「中止」する際の「正当な理由」のハードルが相当高いともいえます。
一方、食品や日用雑貨、アパレル製品などは、ブランドスイッチのリスクは仕方ないとした上で「中止」の判断が可能です。
「中止」ではなく「中断」の判断をする際も、業界による対応に幅があります。「忠告」や「警告」の仕方や回数などにも違いがあると考えられます。当コラムでは、業界による対応の違いがあることを前提としてお伝えしていることをご理解ください。
■最後に
各企業において、お客さまに納得いただけない場合の具体的なケースを集めることをお勧めします。応答内容をQ&Aにまとめておくと、今後同様の事案への対応に活用できます。お客さまへの説明や提案は大事ですが、納得していただけない場合、個人判断ではなく組織として仕方ないと判断することが大事です。
マニュアルに記載することで管理者も判断がしやすくなり、過度の負荷がかかることはありません。カスタマーハラスメントを未然に防ぐためにも組織で対応することが肝要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。